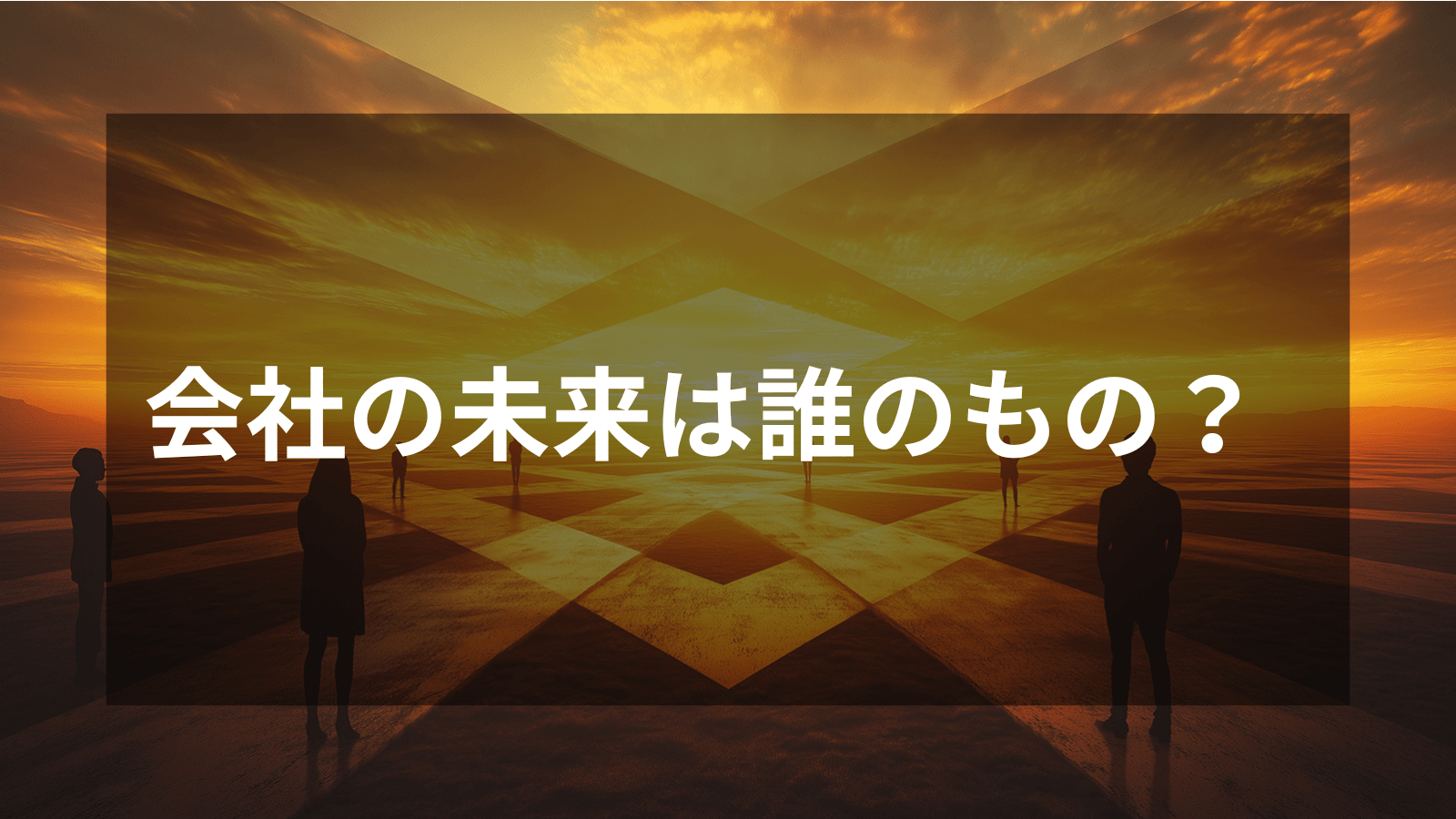第1回:相続で全てが明らかに~なぜ隠し財産がバレてしまうのか~
相続は単なる遺産分割ではなく、亡くなった方の一生涯にわたる財産の完全な「棚卸し」です。どんなに巧妙に隠していたつもりの財産も、相続をきっかけに思わぬ形で表面化することがあります。全3回シリーズの第1回では、なぜ被相続人が意図せずとも隠し財産が発覚してしまうのか、その実態と対策について解説します。
相続とは「人生の財産の棚卸し」
相続が発生すると、亡くなった方の全ての財産を明らかにしなければならないという大きなプロセスが始まります。
これは単に遺産を分けるためだけでなく、相続税を正しく計算し、納めるための重要な作業です。
そのためには、被相続人(亡くなった方)の
- 預貯金
- 不動産
- 株式・有価証券
- 生命保険
- 負債(借入金)
など、すべてを漏れなく調査し、「財産目録」を作成しなければなりません。
これを怠れば、相続税の申告漏れや、家族間の争いの原因になりますし、
最悪の場合は税務署からの調査が入り、過少申告加算税や重加算税が課されることもあります。
「隠し財産」が発覚する背景
実際の相続の現場では、家族が知らなかった財産や、
名義を変えて隠していたつもりの財産が発覚するケースが少なくありません。
なぜ、そうした隠し財産がバレてしまうのでしょうか?
それは、相続が「一生の財産の棚卸し」であるからです。
亡くなった時点の財産を把握するだけでなく、
その財産がどのように形成されてきたのか、過去の流れまで遡って調べるのが相続の特徴です。
他人名義の財産まで「見える化」される?
よくあるのが、名義預金や他人名義の財産です。
たとえば
- 子や孫の名義で預金口座を開設し、そこにお金を移している
- 親族名義の不動産を実質的に自分が使っている
こうした財産は「名義が違うから問題ない」と思われがちですが、
税務署や金融機関は名義ではなく「実質的な所有者」が誰かを見ています。
税務署は、亡くなった方が通帳を管理していたか?
印鑑は誰が持っていたか?
入出金の指示は誰が出していたか?
を調べます。
さらに、預金通帳を開設した時の申込書の筆跡や印鑑を取り寄せ、
誰が実質的に管理していたかまで確認することもあります。
これは、証券会社の口座でも同様です。
家族信託を活用することで、将来的な認知症リスクを考慮しつつ、生前の財産管理と相続をスムーズに行うことができます。事業承継や不動産の管理にも適しており、専門家のサポートを受けながら設計することが大切です。
【事例】名義預金が発覚したケース
80代で亡くなったA社長は、生前に「この口座は子どもの名義だから自分の財産じゃない」と言っていました。
しかし、その口座の通帳も印鑑も、すべてA社長が管理しており、入出金の指示も自分で行っていました。
税務署は、通帳開設時の申込書を取り寄せ、A社長の筆跡で申込がされていたことを確認。
結果、その口座は名義預金と認定され、相続財産に加算されました。
これにより、相続税が追加で課され、さらに過少申告加算税10%も課されました。
税務署は「お金の流れ」を把握している
税務署は、単に財産の額を調べるだけではありません。
財産がどのように形成されたか、その流れを把握することができます。
例えば
- 家族全員の預金残高を過去5年分一覧表にして、
誰の預金が減り、誰の預金が増えているかをチェック - 預金を現金で引き出した形跡がある場合、
その後の現金の使途を確認
また、
- 有価証券を売却して現金化した場合
- 不動産を売却して現金化した場合
これらの資産が金融機関に預けられていないと、
「現金がある」と税務署は推定し、調査が入る可能性が高くなります。
税務署の調査は「深く」「広く」
税務署の調査は、亡くなった方だけでなく、家族・法人の取引関係まで調べることができます。
会社を経営している場合、法人と個人の資産の流れもチェックされ、
例えば法人から個人への資金移動などが確認されます。
【事例】法人から個人への送金が発覚したケース
B社の社長が亡くなった際、会社の口座と個人の口座を調査した結果、
会社の利益が個人の名義預金に流れていたことが判明。
これは会社からの資産移動と認定され、相続財産に加算されました。
まとめ:相続は「財産を整理するチャンス」
このように、相続では隠していたつもりの財産が遡って発覚する可能性があります。
「名義を変えたから大丈夫」と安心せず、
今のうちに財産を整理し、正しい相続対策を行うことが大切です。
相続はトラブルが起きてからでは遅いのです。
「名義預金が心配…」「会社と個人の資産が混ざっているかも…」という方は、
ぜひ早めに相続専門の税理士やコンサルタントにご相談ください。
【無料相談受付中】
名義預金についてのご相談はこちらから